フォトブックを作る際、最も時間がかかり、多くの方が「どの写真を選べばいいのか分からない…」と悩むのが写真選びのステップです。スマートフォンの中には数百、数千枚もの写真が溜まっており、その中から厳選するのは本当に大変な作業です。
このページでは、フォトブックサービス比較ガイドの関連情報として、100冊以上のフォトブック作成経験に基づく「写真選びのコツ」と「選定作業の効率化方法」をご紹介します。特に忙しい子育て世代の皆さんが、限られた時間の中で迷わず素敵なフォトブックを作れるよう、実践的なアドバイスをまとめました。

ミーさん
子どもの写真、スマホに何千枚も溜まってて、どの写真をフォトブックに入れるか選ぶだけで心が折れそうになるんです。全部入れたいけど、それも無理だし…。効率的に選ぶコツってあるんですか?

シーサー先生
それは多くの方が抱える悩みですね。100冊以上のフォトブックを作ってきた経験から言うと、「全部入れたい」という気持ちが写真選びを難しくしている大きな原因です。今日は、選ぶ基準と効率化のテクニックをお伝えしますので、ぜひ実践してみてください!
目次
フォトブック用写真選びの基本的な考え方
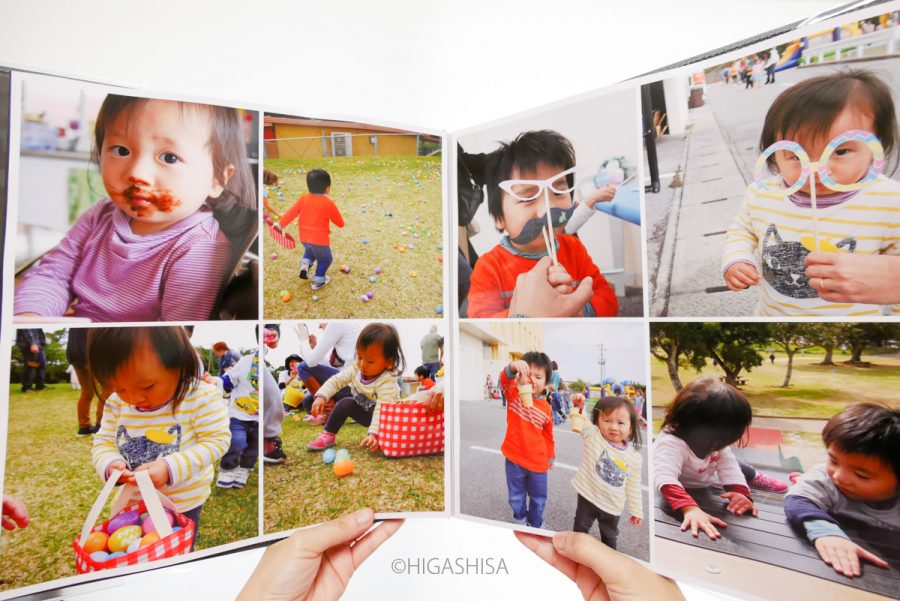
フォトブック作りで最初につまずくのが「どの写真を選べばいいのか」という問題です。スマートフォンには大量の写真が保存されていて、すべてが思い出につながる大切なものばかり。そんな中から選ぶのは本当に大変です。
しかし、写真選びに明確な基準と効率的な方法があれば、この作業はぐっと楽になります。まずは基本的な考え方から見ていきましょう。
写真選びで陥りがちな3つの罠
写真選びが進まない原因は、以下の3つの「罠」に陥りやすいからです。
- 完璧主義の罠:「すべての思い出を漏れなく入れたい」という気持ちから選択ができなくなる
- 比較の罠:似たような写真が複数あると「どちらが良いか」延々と比較してしまう
- 先送りの罠:「今ではなく、時間のあるときにじっくり選ぼう」と考えて永遠に先延ばしにしてしまう
これらの罠から抜け出すには、「完璧なフォトブック」よりも「完成するフォトブック」を優先する考え方が大切です。100冊以上のフォトブックを作ってきた経験から言えるのは、「選び方に正解はない」ということ。大切なのは、自分なりの選定基準を持ち、効率的に作業を進めることです。
基本原則:目的に合わせた選択
写真選びで最も重要なのは、そのフォトブックの「目的」を明確にすることです。目的によって、選ぶべき写真の基準が変わってきます。
- 子どもの成長記録:発達の節目や日常の変化が分かる写真を中心に
- 家族旅行の記録:場所や体験が分かる写真、家族の表情が生き生きと映った写真を優先
- 年間アルバム:季節ごとのイベントや変化が分かる代表的な写真をバランスよく
- お祝い・記念日:特別な日の雰囲気や参加者の様子が伝わる写真を選択
- 祖父母へのプレゼント:子どもの表情がはっきり見える写真、家族の絆が感じられる写真を重視
目的を明確にすることで、「どの写真が必要か」という基準ができ、選択が格段に楽になります。例えば「子どもの1年間の成長記録」というテーマなら、月齢ごとの変化が分かる写真を中心に選べばいいですし、「家族旅行の思い出」なら、場所や体験が分かる写真を優先すればいいのです。

ミーさん
なるほど!最初に目的をしっかり決めておくと選びやすくなるんですね。でも、子どもの日常写真をまとめたいときは、どんな写真を選べばいいですか?

シーサー先生
日常の記録なら、「その時期らしさ」が伝わる写真を選ぶといいですよ。子どもが好きだったおもちゃで遊ぶ様子、よく着ていた服、お気に入りの食べ物を食べている瞬間など、後から見返したときに「あの頃はこれが好きだったな」と思い出せる写真が特におすすめです!
フォトブックに最適な写真の選定基準
目的が決まったら、次は具体的にどのような写真を選べばいいのか、その基準を見ていきましょう。以下の選定基準は、100冊以上のフォトブック作成経験から導き出した、特に子育て世代におすすめのポイントです。
選ぶべき写真の10の基準
以下の10の基準を参考に、フォトブックに入れる写真を選んでみましょう。すべての基準を満たす必要はなく、あなたのフォトブックの目的に合った基準を優先してください。
- 表情が良く見える写真:特に子どもの表情がはっきりと映っている写真は必須です
- ストーリー性のある写真:その場の状況や雰囲気が伝わる写真は記憶を呼び起こします
- 背景に意味がある写真:場所や環境が分かる写真は思い出を補強します
- 時代感が出ている写真:当時の流行やファッション、流行っていたキャラクターグッズなどが映り込んでいる写真は、時代の空気感を記録します
- 季節を感じられる写真:季節の行事や風景が映っている写真は、一年の流れを表現できます
- 人間関係が分かる写真:家族や友人との交流が見える写真は、人間関係の記録として価値があります
- 日常の何気ない瞬間の写真:特別なイベントだけでなく、普段の生活の一コマも大切な記録になります
- 成長や変化が分かる写真:同じ場所や同じポーズで時期を変えて撮った写真は、変化が比較できる貴重な記録です
- 色バランスの良い写真:見開きページのカラーバランスを考慮し、色調が似た写真をグループ化すると統一感が出ます
- 印刷に適した明るさと鮮明さの写真:暗すぎる写真や極端にぼやけた写真は避け、印刷した際に見やすい写真を選びましょう
これらの基準のうち、特に重要なのは1、2、10の基準です。表情がよく見え、状況が伝わり、かつ印刷したときに見やすい写真であれば、基本的には良い選択と言えるでしょう。
避けるべき写真の特徴
一方で、フォトブックには向かない写真の特徴もあります。以下のような写真は、よほど思い入れがない限り、除外を検討しましょう。
- 極端に暗い写真:印刷するとさらに暗く見えることが多い
- 大きくブレている写真:小さなブレなら許容範囲だが、大きなブレは印刷するとより目立つ
- 極端にピントがずれている写真:意図的なボケ感は芸術的でも、単なるピントずれは印刷に向かない
- 極端に明るすぎる写真:露出オーバーで白とびした部分は印刷でも再現されない
- 極端に小さな被写体の写真:遠くの小さな被写体は、印刷すると見分けにくくなる
- 多すぎる類似写真:ほぼ同じ構図の写真を複数選ぶのは避ける
- 思い出としての価値が低い写真:例えば、料理の写真だけなど、人やストーリーが入っていない写真は選別を検討
ただし、これらの「避けるべき特徴」があっても、その写真だけが捉えた貴重な瞬間であれば、採用する価値はあります。例えば、暗くてもブレていても「赤ちゃんが初めて笑った瞬間」や「子どもが初めて歩いた瞬間」などの貴重な写真は、技術的な問題よりも思い出としての価値を優先すべきでしょう。
子どもの成長記録に特に重要な写真
特に子育て世代の方々にとって、子どもの成長記録はフォトブックの大きな目的の一つです。以下は、子どもの成長記録に特に重要な写真の例です。
- 発達の節目:初めて笑った、首が座った、寝返りをうった、つかまり立ちをした、歩いた、話した、などの瞬間
- 身体的な変化:身長・体重測定の様子、歯が生えた/抜けた瞬間、髪型の変化など
- 興味・好みの変化:好きなおもちゃ、好きな食べ物、好きなキャラクターが分かる写真
- 日常の習慣:食事、入浴、読み聞かせ、お昼寝など、日々の生活が分かる写真
- 家族との関わり:親、兄弟姉妹、祖父母など家族との触れ合いの様子
- 季節の行事・イベント:誕生日、七五三、入園・入学式、クリスマス、お正月など
- 表情の豊かさ:笑顔、泣き顔、驚き顔、真剣な表情など、様々な感情表現
- 環境の変化:引っ越し、部屋の変化、園・学校の様子など、子どもを取り巻く環境
子どもの成長記録の場合、「見た目の良さ」よりも「記録としての価値」を優先することも多いでしょう。例えば、初めて自分で服を着た時の少しだけぎこちない様子や、初めてスプーンを使った時のぐちゃぐちゃになった食事の風景など、必ずしも「きれいな写真」ではなくても、成長の記録として非常に価値のある写真はたくさんあります。
写真選びの効率的なワークフロー
選ぶべき写真の基準が分かったところで、次は実際の選定作業を効率的に進めるためのワークフローを紹介します。特に子育て中の忙しい方が、限られた時間の中で効率よく写真を選ぶための手順です。
写真選びの5ステップメソッド
以下の5つのステップに従って作業を進めることで、効率的に写真選びが完了します。
- STEP
目的と範囲を明確にする
まず、フォトブックの目的(子どもの1年間の記録、旅行の思い出など)と、対象期間(〇〇年〇月〜〇〇年〇月)を明確に決めます。この時点で、使用する写真の枚数の目安も決めておくと良いでしょう。例えば、24ページのフォトブックなら40〜60枚程度が目安です。
- STEP
大まかな振り分け(第一選別)
対象期間の写真を「使う可能性あり」と「使わない」の2つに大まかに振り分けます。この段階では深く考えず、直感で「これは入れたい」と思った写真を選びます。迷った写真は「使う可能性あり」に入れておきましょう。この段階では多めに選んでOKです。
- STEP
グループ分け
「使う可能性あり」の写真を、テーマや時系列でグループ分けします。例えば、「誕生日」「公園遊び」「日常の様子」などのカテゴリーや、月ごとのグループに分けると良いでしょう。この時点で、グループごとに使用する枚数の目安も決めておくと後の選別が楽になります。
- STEP
詳細選別(第二選別)
各グループ内で、最終的に使う写真を選びます。類似写真がある場合は、表情が良いもの、構図が良いものを1枚だけ残します。このとき、先に紹介した「選ぶべき写真の10の基準」と「避けるべき写真の特徴」を参考にしてください。グループごとの目安枚数を意識して選ぶことで、バランスの良い写真選びができます。
- STEP
最終確認と調整
選んだ写真全体を見渡して、バランスを確認します。時系列に偏りがないか、同じような構図や表情の写真が多すぎないか、重要なイベントが抜けていないかなどをチェックします。必要に応じて写真の追加や削除を行い、全体のバランスを整えましょう。
このワークフローを一気に完了させる必要はありません。特に第二選別は時間がかかるので、1日で全部やろうとせず、グループごとに少しずつ進めるなど、無理のないペースで行いましょう。

ミーさん
なるほど!段階的に選んでいくのがポイントなんですね。でも、実際に選ぶ時間がなかなか取れないんです。子どもが寝た後の短い時間でも効率よく選ぶ方法はありますか?

シーサー先生
その悩みをよく聞きます!次は、忙しい子育て世代のために開発した「時短テクニック」をご紹介しますね。15分×4回程度の短い時間でも、効率よく写真選びができる方法をお伝えします!
忙しい子育て世代のための時短テクニック
子育て中は、まとまった時間を確保するのが難しいものです。そこで、少ない時間を効率的に使って写真選びを進めるための実践的なテクニックをご紹介します。これらのテクニックは、100冊以上のフォトブック作成経験から生まれた、忙しい親のための時短ノウハウです。
1. スマートフォンの機能を活用した事前準備
スマートフォンの標準機能やアプリを活用して、写真選びの下準備をしておくと、後の作業がぐっと楽になります。
- お気に入りマーク活用法:iPhoneの「ハート」マークやAndroidの「星」マークで、候補写真にマークをつけておく
- アルバム分類法:スマホの標準アプリでフォトブック用のアルバムを作成し、そこに候補写真をコピーする
- 名前付けフィルタリング:重要な写真にはファイル名を付けて(例:「1歳誕生日_メインケーキ」)、検索しやすくする
- 写真整理アプリの活用:専用の写真整理アプリを使って、効率的に分類・選別する
- 自動分類の活用:Googleフォトなどの自動認識機能を使い、人物や場所で写真を自動分類させる
特に「お気に入りマーク」と「専用アルバム作成」は、スキマ時間を活用できる点で非常に便利です。例えば、電車の中や子どもが少し遊んでいる間など、ほんの数分の時間でもサクサクとマーキングできます。このような小さな積み重ねが、後の本格的な選別作業を大幅に効率化します。
2. 時間制限とタイマー活用法
写真選びに時間がかかる大きな理由の一つは、「選択に迷う時間」が長くなりがちなこと。そこで、タイマーを設定して時間制限を設けることで、決断力を高める方法が効果的です。
- 15分ルール:1回の作業時間を15分に限定し、その時間内でできるだけ多くの写真選択を行う
- 3秒ディシジョン:1枚の写真を見て「使う/使わない」を3秒以内に決める練習をする
- 50枚チャレンジ:15分で50枚の写真を選別することを目標にする
- ポモドーロテクニック応用:25分集中、5分休憩のサイクルで写真選びを進める
- 時間固定・進捗可変方式:時間を固定し、その時間内でどこまで進められるかを意識する(例:今日は20時00分から20時15分までフォトブック作業と決める)
時間制限を設けることで、「完璧な選択」よりも「決断すること」を優先する姿勢が身につきます。特に「3秒ディシジョン」は、最初は難しく感じるかもしれませんが、練習を重ねることで写真を見る目が鍛えられ、直感的な判断ができるようになります。
3. 写真選びの分業と外部化
写真選びは必ずしも一人で行う必要はありません。家族や友人と分担したり、一部の判断を外部化したりすることで、効率アップと客観性の向上が期待できます。
- パートナーとの分業:例えば、一次選別はパパが担当し、最終選別はママが行うなど、役割分担を決める
- 子どもを巻き込む:年齢に応じて、子ども自身に「好きな写真」を選んでもらう(特に小学生以上なら参加可能)
- 外部の目を活用:親しい友人や家族に候補写真を見せて意見をもらう(LINE等のグループ機能が便利)
- 自動選別サービスの活用:一部のフォトブックサービスでは、AIが自動で最適な写真を選んでくれる機能もある(各サービスの比較を参照)
- 選別の外注:大量の写真から厳選が必要な場合、選別まで含むフォトブック代行サービスを検討する
特にパートナーとの分業は、一人での作業よりも大幅な時間短縮になります。例えば、パパが月1回、15分程度で「その月の写真を大まかに選ぶ」作業を担当し、ママがそれをもとに「最終選別とレイアウト」を担当するという方法は、多くのご家庭で成功しています。

ミーさん
夫に手伝ってもらうのはいいアイデアですね!でも、うちの夫は「全部同じような写真に見える」って言うんですよ…。そういう人でも参加できる方法ってありますか?

シーサー先生
それはよくある悩みですね!そんな場合は「明確な基準」を設けるといいですよ。例えば「子どもの表情がよく見える写真だけを選ぶ」「風景が入っている写真を選ぶ」など、具体的で単純な基準を伝えると参加しやすくなります。また、「この中から3枚選んで」のように、選ぶ枚数を限定するのも効果的ですよ!
4. 写真選びルールの明確化
写真選びの作業を効率化するには、あらかじめ「選び方のルール」を決めておくことが非常に効果的です。明確なルールがあると、一つひとつの写真について長く悩むことなく、サクサクと選別作業が進みます。
- 数値目標の設定:「月ごとに5枚」「イベントごとに3枚」など、選ぶ枚数を明確に決める
- 1/3法則:似たような写真が3枚あれば、必ず1枚だけを選ぶと決める
- ベスト1選出法:各シーンやカテゴリから必ず「最も良い1枚」だけを選ぶと決める
- 具体的な選別基準:「笑顔の写真を優先」「全身が写っている写真を選ぶ」など、明確な基準を決める
- 除外ルールの明確化:「ブレている写真は使わない」「極端に暗い写真は使わない」など、除外する条件を決めておく
これらのルールは、特に子どもの写真を選ぶ際に有効です。子どもの写真は撮影枚数が多くなりがちで、「どれも可愛い」と感じて選べなくなることがよくあります。しかし、「同じ場所で撮った写真は1枚だけ」「表情がはっきり見える写真を優先」などのルールを設けることで、選択のハードルが下がります。
5. 定期的な写真整理の習慣化
最も効果的な時短方法は、写真が大量に溜まる前に、定期的に整理する習慣を身につけることです。これにより、フォトブック作成時の写真選びが格段に楽になります。
- 月末整理デー:毎月最終日に、その月の写真を整理・選別する時間を設ける
- 就寝前5分ルーティン:子どもを寝かしつけた後、毎日5分だけ写真整理の時間を設ける
- デジタルデトックスデー:月に1回「デジタル整理の日」を設け、写真の整理・バックアップを行う
- イベント後24時間ルール:行事や旅行の後、24時間以内に写真の一次選別を完了させる
- アプリ通知活用:写真整理アプリのリマインダー機能を使い、定期的な整理を促す
定期的な写真整理は、最初は面倒に感じるかもしれませんが、習慣化することで自然と負担感は減っていきます。特に「月末整理デー」を家族の習慣にして、その月の思い出を振り返りながら写真を整理する時間を持つことは、フォトブック作成だけでなく、家族のコミュニケーションにも良い影響を与えます。
写真選びに関するよくある質問
写真選びに関して、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの疑問を解消することで、さらに効率良く写真選びを進めることができます。
Q
フォトブックのページ数に対して、どれくらいの写真を選ぶのが適切ですか?
A
一般的な目安として、ページ数の1.5〜2倍の写真を選ぶと良いでしょう。例えば、24ページのフォトブックなら35〜50枚程度の写真を選びます。ただし、1ページに何枚の写真を配置するかによっても変わります。全面1枚使いのシンプルなレイアウトなら24枚程度、複数枚レイアウトを多用するなら50枚以上必要になることもあります。まずはフォトブックサービスのテンプレートやレイアウトを確認してから、必要な枚数を決めると良いでしょう。
Q
スマホの写真が多すぎて整理が追いつきません。効率的に大量の写真を選別する方法はありますか?
A
大量の写真の選別には「多段階選別法」がおすすめです。まず最初に極端に粗い選別(使えそうかどうかの2択)で写真の量を減らし、次に中程度の選別(良い・普通・除外の3段階)を行い、最後に詳細な選別をします。また、顔認識機能のあるアプリ(GoogleフォトやApple写真など)を使うと、特定の人物が写っている写真だけを自動で抽出できるので便利です。詳しい写真整理術はスマホ写真の整理術の記事をご覧ください。
Q
写真の解像度やサイズが様々ですが、フォトブック用に選ぶ際に注意すべき点はありますか?
A
フォトブックに使う写真は、一般的に画素数が多いほど鮮明に印刷されます。最近のスマートフォンで撮影した写真なら、ほとんどの場合問題ありません。ただし、SNSからダウンロードした写真やスクリーンショットは解像度が低いことがあるので注意が必要です。特に写真を大きく配置したい場合は、元の解像度が高い写真を選びましょう。また、トリミング(切り抜き)を多用すると解像度が下がるので、トリミングが必要な写真は元の解像度が高いものを選ぶことをおすすめします。各フォトブックサービスで推奨される解像度は異なるので、事前に確認しておくと安心です。
Q
子どもの写真で「絶対に入れておくべき」写真はありますか?
A
子どもの成長記録として特に重要なのは、成長の節目となる写真です。例えば、誕生日、初めての歯、初めての歩行、入園・入学式などの特別な日の写真は必ず入れておきたいものです。また、その時期の「日常」を示す写真も貴重な記録となります。例えば、よく遊んでいたおもちゃ、好きだった食べ物、よく着ていた服などの写真は、その時代の空気感を残す大切な記録です。多くの親は「もっと日常の写真を残しておけばよかった」と後悔するので、特別なイベントだけでなく、普段の生活の様子もバランスよく選ぶことをおすすめします。詳しくは子どもの成長記録フォトブックの記事を参考にしてください。
Q
年間フォトブックを作る際、写真の選び方で気をつけるべきポイントはありますか?
A
年間フォトブックでは、時系列のバランスが特に重要です。各月や季節ごとにページ数や写真枚数を均等に割り当てておくと、年間を通してバランスの良いフォトブックになります。例えば、12か月のフォトブックなら、各月2ページずつと計画し、各月3〜6枚程度の写真を選ぶという方法です。また、季節感のある写真(桜、プール、紅葉、雪など)を意識的に入れると、1年の流れが感じられるフォトブックになります。月ごとの主要イベント(誕生日、旅行、行事など)をハイライトとして必ず入れつつ、日常の写真もバランスよく選ぶと、その年の生活が自然と記録された素敵なフォトブックになります。詳しくはフォトブックサービス比較で紹介している年間フォトブックに最適なサービスも参考にしてください。
写真選びをサポートするツールとアプリ
写真選びの効率を高めるために、役立つツールやアプリを活用することもおすすめです。以下は、特に子育て世代におすすめのツールです。
スマートフォン標準アプリの活用
まずは、スマートフォンに標準搭載されている写真アプリの機能を最大限活用しましょう。
- iPhoneの「写真」アプリ:
- 「お気に入り」機能:ハートマークで候補写真をマーク
- 「アルバム」機能:専用のフォトブック用アルバムを作成
- 「人物」認識:特定の人物の写真だけを自動的に集める
- 「メモリー」機能:AIが自動で作成したフォトコレクションからインスピレーションを得る
- Androidの「Google フォト」:
- 「お気に入り」機能:星マークで候補写真をマーク
- 「アルバム」機能:専用アルバムで整理
- 「人物」グループ:顔認識で人物ごとに自動分類
- 検索機能:「公園」「海」など場所や状況でも検索可能
特にGoogleフォトの検索機能は非常に優秀で、「笑顔」「食べ物」「ビーチ」などのキーワードで写真を検索できます。これを活用すれば、テーマごとの写真選びが格段に効率化されます。
専用写真整理アプリの活用
より高度な写真選別や整理を行いたい場合は、専用の写真整理アプリも検討する価値があります。
- 整理特化型アプリ:「Slidebox」(素早く写真を選別できるスワイプ機能)、「Gemini」(AIによる写真分析と整理機能)
- フォトブック作成アプリ:多くのフォトブックサービスは独自アプリを提供しており、写真選びから作成まで一貫して行えます(各サービスの比較を参照)
- 家族アルバムアプリ:「みてね」「Famm」などの家族向け写真共有アプリも、整理機能が充実しています
- 写真編集アプリ:「Lightroom」「Snapseed」などの編集アプリは、写真のレーティング(星評価)機能で選別にも活用できます
これらのアプリは基本機能は無料で利用できるものが多いですが、より高度な機能を使うには有料プランへの加入が必要な場合もあります。自分の使い方や優先順位に合わせて、最適なツールを選びましょう。
パソコンを活用した大量写真の効率的整理
大量の写真を一度に整理したい場合や、より細かい管理を行いたい場合は、パソコンの活用も検討する価値があります。
- Adobe Lightroom:写真のカタログ化、タグ付け、レーティングなどの機能が充実
- Googleフォト(Web版):大きな画面で写真を確認しながら選別・整理が可能
- Apple写真(Mac):MacユーザーならiPhoneの写真とシームレスに連携
- フォトブックメーカーのPC版ソフト:各フォトブックサービスが提供するデスクトップソフトは、写真選びから作成までをスムーズに行える
パソコンの大きな画面で作業すると、細かい写真の違いも見分けやすく、同時に複数の写真を比較検討することもできます。特に年末の大掃除や年度末など、まとまった整理を行う際には有効です。

ミーさん
ツールはたくさんあるんですね!でも結局、どのサービスのフォトブックが写真選びしやすいですか?アプリの使いやすさも重要だと思うんですが…

シーサー先生
おっしゃる通り、アプリの使いやすさは大切ですね!写真選びのしやすさという観点では、「ノハナ」のアプリは直感的な操作性で初心者にも使いやすく、「マイブック」は豊富なテンプレートで迷わず選べる工夫があります。「しまうまプリント」は経済的で頻繁に作るなら負担が少ないですよ。各サービスの詳細はフォトブックサービス比較ガイドで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください!
まとめ:写真選びを効率化して素敵なフォトブックを作ろう
フォトブック作成における最大の難関である「写真選び」のコツと効率化テクニックをご紹介してきました。最後に、ポイントを整理しておきましょう。
- 目的を明確に:フォトブックの目的(成長記録、旅行記録など)を明確にすることで、選ぶべき写真の基準が明確になります
- 選定基準を持つ:表情が良く見える、ストーリー性がある、印刷に適しているなどの基準に基づいて選びましょう
- 効率的なワークフロー:5ステップメソッド(目的設定→大まかな振り分け→グループ分け→詳細選別→最終確認)で効率的に選別を進めましょう
- 時短テクニックの活用:スマホの機能活用、時間制限の設定、写真選びの分業など、忙しい子育て世代向けの時短テクニックを取り入れましょう
- 習慣化の重要性:写真が大量に溜まる前に、定期的に整理・選別する習慣を身につけることが最大の時短になります
- 便利なツールの活用:スマートフォンの標準機能や専用アプリを活用して、写真選びを効率化しましょう
写真選びは、最初は大変に感じるかもしれません。しかし、本記事で紹介したテクニックを実践することで、徐々に効率的に進められるようになります。完璧を求めすぎず、「選ぶこと」自体を楽しむ気持ちで取り組んでみてください。
そして、どんなに写真選びに時間をかけても、フォトブックはプロが作る写真集のような完璧さを目指す必要はありません。少々のミスや偏りがあっても、そこには家族の思い出が詰まっています。大切なのは「形にすること」。完璧なフォトブックよりも、完成したフォトブックの方がずっと価値があるのです。
フォトブックサービスの選び方や具体的な作成方法については、以下の関連記事も参考にしてください。
- 【2025年最新】子育て家族におすすめのフォトブックサービス徹底比較
- フォトブック 失敗しない作り方 6つのコツ
- 子どもの成長記録フォトブック作成ガイド
- スマホ写真の整理術:子育て世代のための効率的な管理方法
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されることがありますが、紹介している商品やサービスに関する評価は、100冊以上の実際の作成経験に基づく正直な感想です。

