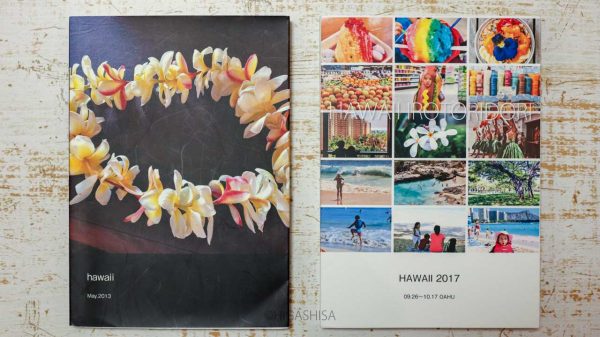フォトブックを1冊作るのは簡単でも、継続して作り続けるのは簡単ではありません。特に子育て中のお母さん・お父さんは「時間がない」「写真が溜まりすぎている」「いつか余裕ができたら作ろう」と思いながら、気づけば1年、2年と経ってしまうことも。
このページでは、フォトブックサービス比較で紹介している各社サービスを活用しながら、子育て世代でも無理なく続けられるフォトブック作成の習慣化方法をご紹介します。100冊以上のフォトブックを7年間で作り続けてきた経験から、「続けるコツ」だけを凝縮してお伝えします。

シーサー先生
フォトブックは1冊だけ作るより、毎年作り続けることで価値が何倍にも高まります。子どもの成長記録も、家族の思い出も、継続することで素晴らしいコレクションになるんですよ。
目次
フォトブックを継続して作るメリット
まずは、フォトブックを継続的に作成することで得られるメリットをご紹介します。これから紹介する「習慣化のコツ」を実践するモチベーションにもなります。
- 成長の連続性が見える:毎年同じフォーマットで作ることで、子どもの成長が一目瞭然
- 整理が楽になる:定期的に写真を整理する習慣がつき、デジタルデータの管理が楽に
- 作るスキルが向上する:回数を重ねるごとにレイアウトや写真選びが上達
- 家族の歴史書になる:年を重ねるごとに、かけがえのない家族の歴史コレクションに
- 写真を撮る目的ができる:「フォトブックに入れよう」という意識で大切な瞬間を逃さなくなる

ミーさん
毎年作り続けることの大切さはわかるんですが、仕事や育児で忙しくて…。「今度時間ができたら作ろう」と思いつつ、もう1年以上経ってしまいました。

シーサー先生
その「今度時間ができたら」症候群、多くの方が陥る落とし穴です。でも大丈夫。これから紹介する7つのコツを実践すれば、忙しい子育て世代でも無理なく継続できますよ。
フォトブック作成が続かない主な原因
まずは、フォトブック作成が続かない主な原因を理解しましょう。自分の状況を客観的に把握することで、効果的な対策ができます。
- 「完全版」へのこだわり:完璧なフォトブックを作ろうとして時間がかかり挫折
- まとまった時間の確保が難しい:子育て中に3時間など続けての作業時間を確保できない
- 写真の選別に時間がかかる:大量の写真から選ぶのに時間がかかりすぎる
- 「今ではない」症候群:「もっと落ち着いたとき」「子どもが大きくなったら」と先延ばし
- 作るハードルの高さ:始めるまでの心理的ハードルが高く感じられる
これらの原因を理解した上で、次からは具体的な7つの習慣化コツを紹介します。
フォトブック作成を習慣化する7つのコツ
コツ1:「完璧」より「継続」を重視する
100冊以上のフォトブックを作ってきた経験から最も重要なことは、完璧なフォトブックを1冊作るよりも、「まあまあ」のクオリティでも継続して作ることの方が圧倒的に価値があるということです。
作りながら徐々に改善していくことで、結果的にクオリティは向上します。初めから完璧を目指すと挫折率が高くなります。
- STEP
「8割の法則」を取り入れる
完成度は「8割」を目標にします。追求すればきりがない細部よりも、まずは完成させることを優先しましょう。
- STEP
テンプレートを活用する
一から全てデザインするのではなく、提供されているテンプレートを活用しましょう。フォトブックのレイアウトデザインのコツを学びながら、少しずつカスタマイズしていけば十分です。
- STEP
「迷ったら両方入れる」ルールを作る
「この写真とあの写真、どちらを使おう?」と迷った場合は、両方入れることにしましょう。選ぶ時間を節約できます。
コツ2:細切れ時間を活用する「15分×4」の法則
子育て中に「3時間のまとまった時間」を確保するのは至難の業です。代わりに「15分×4回」などの細切れ時間を有効活用する方法が効果的です。
- STEP
写真を選ぶ
通勤中や子どもの習い事の待ち時間などに、スマホで写真選びをしましょう。スマホ写真の整理術を活用すれば、効率的に進められます。
- STEP
ラフレイアウトを決める
選んだ写真をどのようにレイアウトするか、大まかに決めます。子どもが寝た後のリラックスタイムなどに進めましょう。
- STEP
詳細レイアウトを調整する
写真の配置や大きさ、文字入れなどの細かい調整をします。フォトブック作成時間短縮テクニックを参考にすると効率的です。
- STEP
最終チェックと注文
全体を見直し、誤字脱字や写真の配置ミスがないかを確認して注文します。完璧を求めすぎず、期限を決めて「今日中に注文する」という決断が大切です。
実際に子育て世代の多くが「子どもが寝た後の15分」「通勤電車での15分」など、細切れ時間を活用して作成しています。スマホアプリ対応のサービスであれば、どこでも作業を継続できるのが強みです。
コツ3:年間計画に組み込む「トリガー」を設定する
フォトブック作成を習慣化するためには、毎年同じタイミングで作り始める「トリガー」を設定すると効果的です。
- 子どもの誕生月:毎年子どもの誕生日に合わせて「1年の成長記録」を作る
- 年度末の3月:新学期が始まる前に「学年の記録」としてまとめる
- 年末年始:1年のまとめとして、年末年始の休暇中に作成する
- 長期休暇開始時:夏休みや冬休みの開始日をフォトブック作りの日と決める
- 特定のイベント後:家族旅行や運動会など、特定のイベント後1週間以内に作り始める
スマートフォンのカレンダーやリマインダーに「フォトブック作成週間」として登録しておくと忘れません。大切なのは「毎年同じタイミング」で作り始めることです。

シーサー先生
私の場合は、子どもの誕生日の1ヶ月前を「フォトブック作成の日」と決めています。毎年その日が近づくと自然と「そろそろフォトブック作成の時期だな」と思い出せるようになりました。
コツ4:写真の「日常的整理」習慣を身につける
フォトブック作成が大変に感じる最大の理由は「溜まりすぎた写真から選ぶ作業」です。これを解決するために日常的な写真整理の習慣を身につけましょう。
- STEP
週に一度の「写真整理タイム」
週末などに15分程度の「写真整理タイム」を設け、その週に撮った写真から不要なものを削除し、良い写真に「お気に入り」マークをつけていきます。
- STEP
月に一度の「フォトブックフォルダ」整理
スマホやクラウドストレージに「フォトブック候補」フォルダを作り、月に一度、お気に入りマークをつけた写真をこのフォルダに入れましょう。
- STEP
「これはフォトブックに入れたい」と思ったらすぐ印をつける
特に思い出深い写真は、撮影直後に「フォトブック候補」としてマークしておきましょう。この習慣が後々の作業を大幅に効率化します。
この写真整理の習慣があれば、フォトブック作成時には既に候補が揃っているため、選ぶ作業が格段に楽になります。スマホ写真の整理術もぜひ参考にしてください。
コツ5:スマホ完結型サービスを選ぶ
習慣化のためには、使いやすいツールを選ぶことも重要です。特に子育て世代にとって、PCを起動して作業する時間を確保するのは難しいため、スマホだけで完結できるサービスを選ぶのがおすすめです。
スマホアプリの使いやすさに定評のあるサービスとしては以下が挙げられます:
| サービス名 | アプリの特徴 | 使いやすさ |
|---|---|---|
| ノハナ | 自動レイアウト機能、シンプルな操作性 | ★★★★★ |
| しまうまプリント | 多彩なテンプレート、Canva連携 | ★★★★☆ |
| Primii | シンプル操作、月額制で1冊無料 | ★★★★☆ |
| TOLOT | 超シンプル設計、1ページ1写真 | ★★★★★ |
アプリの使いやすさ評価は、100冊以上の実際の作成経験に基づくものです。各アプリの詳細や最新情報については、フォトブックサービス比較をご参照ください。
- 途中保存と再開のしやすさ:細切れ時間で作業するため、保存・再開がスムーズなアプリを選ぶ
- 操作のシンプルさ:複雑な操作が必要なアプリは疲れている時に挫折しやすい
- 自動レイアウト機能:基本レイアウトを自動で作ってくれる機能があると時短に
- クラウド連携:スマホとPCを行き来できるとより使いやすい
コツ6:同じフォーマットで統一感を出す
毎年フォトブックを作る際、「同じフォーマット」で作ることをおすすめします。これには大きく3つのメリットがあります:
- 並べたときに統一感があり、本棚が美しくなる
- テンプレートを再利用できるため作成時間が短縮できる
- 年ごとの比較がしやすく、成長や変化が一目瞭然
初年度に使ったフォーマット(サイズ、表紙デザイン、基本レイアウトなど)を記録しておき、翌年以降も同じものを選びましょう。しまうまプリントフォトブックなどシンプルで続けやすいサービスが特におすすめです。

ミーさん
同じフォーマットで作るのって素敵ですね!でも毎回同じデザインだと飽きてしまいそう…

シーサー先生
基本フォーマット(サイズと表紙のデザイン)は統一しつつ、内容やレイアウトに変化をつけるのが理想的です。たとえば表紙カラーだけ年ごとに変えるのも良いですよ。
コツ7:家族を巻き込み、「共同作業」にする
フォトブック作りを一人で抱え込まず、家族を巻き込んで共同作業にすることで、継続のハードルが下がります。子どもが成長するにつれて、一緒に作る楽しさも増していきます。
- 写真選びを子どもと一緒に:「この中でどの写真がいい?」と子どもに選んでもらう
- パパの担当ページを作る:パパが撮った写真のページは、パパに選んでもらう
- コメント入れを分担:家族の一言コメントを入れることで愛着が湧く
- 家族のイベント後の「フォトブックタイム」:旅行や行事の後に家族でフォトブック作りの時間を設ける
- 「フォトブック発表会」を実施:完成したフォトブックを家族で見る時間を作り、次回作成の動機づけに
特に子どもが自分の写真集に興味を持つようになると、「次はいつ作るの?」と子どもから催促されることもあります。そうなれば習慣化は成功です。
子どもが写真選びに参加することで、「子どもにとって大切な瞬間」に気づかされることも多く、大人の視点だけでは気づかない価値あるフォトブックになります。
年間フォトブック作成カレンダーの例
ここでは、実際に習慣化に成功している方の年間カレンダー例をご紹介します。自分の生活リズムに合わせてカスタマイズしてみてください。
| 時期 | 作業内容 | 所要時間目安 |
|---|---|---|
| 毎週日曜夜 | 週の写真整理・お気に入り登録 | 15分 |
| 毎月末 | 月のベスト写真を「フォトブック候補」フォルダへ | 15分 |
| 4月(年度始め) | 前年度フォトブックの計画立案 | 30分 |
| 5月連休 | 写真選定・大まかなレイアウト決め | 1時間 |
| 6月 | 詳細レイアウト・文字入れ | 1時間 |
| 7月 | 最終チェック・注文 | 30分 |
| 8月(夏休み) | 前半期のミニフォトブック作成(任意) | 2時間 |
| 12月 | 後半期の写真整理・選定 | 1時間 |
| 1月(お正月) | 年間フォトブック作成・注文 | 2時間 |
年に2回(7月と1月)などの複数回に分けて作成する方法もおすすめです。1回あたりの作業量が減り、負担感が軽減されます。
習慣化に失敗したときの対処法
「去年は作れなかった…」「もう2年も作っていない…」というケースもあるでしょう。そんな時の対処法をご紹介します。
Q
もう1年以上フォトブックを作っていません。溜まった写真が多すぎて手がつけられません…
A
「全部を網羅しなければ」という考えを手放しましょう。溜まった期間が長い場合は、「ベストセレクション版」として各月5枚など、厳選した写真だけでフォトブックを作るのがおすすめです。まずは1冊作ることで流れを作り、そこから習慣化していきましょう。
Q
フォトブック作りをはじめたものの、途中で飽きてしまいました。モチベーションを維持するコツはありますか?
A
1回の作業時間を短く区切り、小さな達成感を得ることがコツです。例えば「今日は5ページだけ完成させる」といった具体的な目標を設定しましょう。また、以前作ったフォトブックを見返すことで「完成させる喜び」を思い出すのも効果的です。
Q
子どもが小さく(0〜2歳)、フォトブック作成の時間が全く取れません。どうすればいいでしょうか?
A
この時期は特に時間確保が難しいですね。この場合は自動作成機能のあるサービス(ノハナやTOLOTなど)を利用するか、作成代行サービスの利用も検討してみてください。また、家族や友人にヘルプを求めるのも一案です。少しずつでも写真整理だけは続けることで、時間に余裕ができたときにスムーズに作成できます。
まとめ:習慣化はスモールステップから
フォトブック作成の習慣化は、完璧を目指すのではなく、小さなステップから始めることが大切です。7つのコツをまとめると:
- 「完璧」より「継続」を重視する
- 細切れ時間を活用する「15分×4」の法則
- 年間計画に組み込む「トリガー」を設定する
- 写真の「日常的整理」習慣を身につける
- スマホ完結型サービスを選ぶ
- 同じフォーマットで統一感を出す
- 家族を巻き込み、「共同作業」にする
これらのコツを実践することで、忙しい子育て世代でも無理なくフォトブック作りを習慣化できます。最初は完璧を目指さず、「とりあえず1冊完成させる」ことからスタートしましょう。
フォトブック作成のサービス選びについてはフォトブックサービス比較を、効率的な写真整理についてはスマホ写真の整理術を参考にしてください。
継続することで、年々コレクションが増えていく喜びを味わいながら、家族の大切な思い出を残していきましょう。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されることがありますが、紹介している商品やサービスに関する評価は、100冊以上の実際の作成経験に基づく正直な感想です。